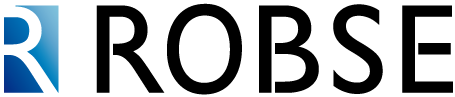――個人も会社も守るためのチェックリスト&初動対応
目次
はじめに
メールは今も仕事と生活のインフラです。その便利さを狙って、個人情報やお金を盗もうとする「フィッシング」「マルウェア(ウイルス)付きメール」「ビジネス詐欺(BEC)」などの手口は、年々巧妙になっています。
本記事では、今日から使える具体的な見分け方ともし開いてしまった時の初動、そして会社としての備えまでを、実例ベースで整理しました。家族・同僚への周知にもそのまま使えるチェックリスト付きです。
まず覚えるべき3原則
- 慌てない(急がせるメールはまず疑う)
「本日中」「アカウントが停止されます」など“時間の圧力”は詐欺の定番。 - 押さない・開かない(リンク・添付は即クリックしない)
まず送り主とURLを確認。添付は“本当に必要か”を自問。 - 別ルートで確かめる(公式アプリ・ブックマークから)
メール内リンクではなく、自分のブックマークや公式アプリからログインして確認。
よくある手口10選(見分けポイント付き)
- 宅配便の不在通知風(再配達案内・伝票番号)
- “リンク先が短縮URL”“画像化されたボタンのみ”は要注意。
- 大手EC/サブスクの「支払い情報更新」(Amazon、Apple、Netflix 等をかたる)
- ドメインが本物かを確認:
amazon.co.jpvsamaz0n.co-jp[.]comのような紛らわしさに注意。
- ドメインが本物かを確認:
- 銀行・クレジットカードの“緊急のお知らせ”
- 本物は個人名の記載や直近の利用の具体があることが多い。漠然とした脅しは偽物の定番。
- 請求書・見積書の差し替え(取引先なりすまし)
- 口座が“いつもと違う”なら電話で担当者本人に確認(メール返信は×)。
- 社長・役員を装った送金依頼(BEC)
- 表示名だけ“社長名”にしてフリーメールで送ってくる。送信元の正確なアドレスを必ず見る。
- クラウドの共有通知を装う(OneDrive/Google Drive/Dropbox)
- “zipで圧縮されたHTML”や“ログイン画面に似せたページ”に誘導し、ID/パスワードを抜き取る。
- セキュリティ警告風(ウイルス検出/パスワード期限切れ)
- 公式はアプリ内通知とメール内容が一致する。メールだけの警告は要確認。
- 採用応募・履歴書を装った添付(人事あて)
docm/xlsm/exe/scr/iso/lnkなどは要警戒。開く前に拡張子を必ず見る。
- 自治体・学校・公共料金の案内を装う
- ドメインが**公式(.go.jp / .lg.jp / 学校ドメイン)**か。ロゴだけ“本物風”に持ってくる偽物に注意。
- QRコード請求・ギフト券購入を促す
- メール→QR→支払いの**“リンク外し”**で警戒心を下げる手口。電話での急かしとセットなら赤信号。
見抜くための「9つのチェック」
- 送信者:表示名に惑わされずメールアドレス本体を確認。微妙な違い(ハイフン/桁/似た文字)に注意。
- 宛先:To/Ccに不自然に多数のアドレス、または自分のアドレス表記が変(役職名だけ、旧姓など)。
- 件名:極端な緊急性・恐怖をあおる表現、過剰な絵文字・記号。
- 本文:ところどころ不自然な日本語、固有名詞の間違い、敬称のズレ。
- 差し迫った期限:今日中・1時間以内など。“即時対応”は詐欺の常套句。
- 行き先URL:マウスオーバーでドメインを確認。短縮URLは展開してから判断。
- 添付拡張子:
ziphtmldocmxlsmexeisolnkは原則開かない。 - 要求内容:ID/パスワード、ワンタイムコード、個人情報、ギフト券購入など**“秘密の要求”**は危険。
- 別ルート検証:正式窓口(公式アプリ、直電、過去の名刺の番号)で事実確認。返信での確認はしない。
URLの安全な見方(1分でできる実践)
- ドメインのコアだけを読む:
https://login.example.co.jp.security-check.com/...→ 本体はsecurity-check.com(アウト) - 似た文字に注意:
0/O、l/1/I、全角/半角、ハイフンの有無。 - 証明書の有無(鍵マーク)は最低限。ただし鍵=安全ではない。内容の整合が最重要。
- ブックマークから入る:メールのリンクは踏まず、自分の登録済みブックマーク経由でアクセスして確認。
添付ファイルの注意点(業務で特に多い)
- Officeマクロ(docm/xlsm/pptm):原則マクロは無効に。取引先でも“初回は共有ストレージ経由”をルール化。
- 圧縮ファイル(zip):パスワード分離送信でも送り主確認が先。不審なら解凍しない。
- 実行形式(exe/scr/iso/lnk):業務で扱うことは稀。来たら疑う→保留が正解。
- HTML添付:偽ログイン画面に誘導する“釣り堀”の定番。開かないが原則。
SMS/電話と組み合わさる“複合型”にも注意
最近はメール+SMS+電話が連動する攻撃も。メールで不安を煽り、SMSで偽サイトへ、電話で“本人確認”と称してワンタイムコードを聞き出す…といった流れです。
コードは“鍵そのもの”。誰にも教えないを徹底しましょう。
個人でできる5つの守り
- 二段階認証(MFA)を必ずON(主要サービスはすべて)
- パスワードは使い回さない(マネージャーを活用)
- メールアプリの画像自動表示をOFF(トラッキング防止)
- 迷惑メール報告を活用(学習精度が上がる)
- 端末の更新(OS・ブラウザ・Office・セキュリティソフトを最新に)
会社としての備え(中小企業向け“現実解”)
- MFAの全社強制(メール・クラウド・会計・勤怠など業務アプリ一式)
- メール認証の整備(SPF/DKIM/DMARC の設定)
- 権限の最小化(送金権限・支払い口座変更は二重承認を必須に)
- セキュリティポリシー(添付は共有ストレージ経由、初取引の口座は電話で再確認など)
- 訓練と周知(月1回、社内チャットで“怪しい実例”共有/四半期にワークショップ)
- バックアップ(ランサム対策のオフライン/世代別バックアップ)
- ログ監視(不審ログイン・転送設定の勝手な追加を検知)
もし開いてしまった/入力してしまった時の初動(状況別)
① リンクをクリックしただけ
- 画面を閉じる → セキュリティソフトでクイックスキャン → その日のうちにフルスキャン
- ブラウザの保存パスワードがある場合、該当サービスは念のため変更
② ID/パスワードを入力してしまった
- 即パスワード変更、MFA未設定なら即設定
- 同じパスワードを使い回していたサービスも総入れ替え
- 可能ならセッション無効化(全デバイスからサインアウト)
③ ワンタイムコードを伝えてしまった
- 乗っ取り中の可能性。アカウント復旧を実施し、支払い情報の不正利用を確認
- 会社アカウントなら情シス/責任者へ即報告
④ 添付ファイルを実行してしまった
- ネットワークから切断(Wi-Fi/有線を外す)
- セキュリティ担当/専門業者に連絡。端末初期化や復元も検討
- 会社なら被疑端末の隔離・ログ保存・影響範囲の洗い出しへ
⑤ 送金・カード情報を渡してしまった
- すぐにカード会社/金融機関へ停止連絡
- 被害記録を残し、**警察相談(#9110)や消費者ホットライン(188)**にも相談
ポイント:時間との勝負。恥ずかしがらず、早く・正しく共有・連絡することが被害拡大を防ぎます。
社内・家庭で貼って使える「一枚チェックリスト」
受信時の7チェック
- 表示名ではなくアドレス本体を見たか
- 宛先/敬称/日本語が不自然でないか
- 期限で焦らせていないか
- URLのドメインを確認したか(マウスオーバー)
- 添付拡張子が安全か(
docm/xlsm/zip/exe/iso/lnk/htmlは要警戒) - 要求が**秘密(認証コード・パスワード・ギフト券)**になっていないか
- **別ルート(公式アプリ・直電)**で確認したか
送信・返信時の3チェック
- 返信先アドレスは元の取引先と同一か
- 口座の変更・高額支払いは二重承認/電話確認を済ませたか
- 社外転送や自動転送設定が勝手に追加されていないか
具体的な周知テンプレ(社内掲示・メール案内に)
件名:不審メール対策のお願い(リンク・添付は開かないで)
本文:
- 期限で急かす/ギフト券購入・口座変更など“秘密の要求”は詐欺の可能性が高いです。
- 送信者は表示名でなくアドレス本体を確認してください。
- メール内リンクは踏まず、公式アプリやブックマークからアクセスしてください。
- 迷ったら、情報システム担当または上長へ転送せずスクショで相談を。
最後に:完璧より「仕組み」でカバーする
人は必ずミスをします。だからこそ、MFAの強制、二重承認、別ルート確認、定期的な周知といった“仕組みの積み重ね”が効きます。
Robseでは、地域の事業者様向けに迷惑メール対策の運用ルール作りや社内向け資料の整備、訓練用コンテンツの制作もお手伝い可能です。
「うちの規模だと何から?」という段階でも大丈夫。**最初の一歩(MFAと二重承認)**からご一緒に進めましょう。
参考:用語ミニ解説
- フィッシング:本物そっくりの画面や文面でログイン情報を盗む手口。
- BEC(Business Email Compromise):社長・取引先になりすまして送金を促すビジネス詐欺。
- マルウェア:不正プログラムの総称。ランサムウェアはデータを暗号化して身代金を要求。
- SPF/DKIM/DMARC:送信元ドメインの正当性を確認するためのメール認証技術。
この記事が、皆さまの毎日の“クリック前の1秒”を守る一助になれば幸いです。必要であれば、貴社の業務フローに合わせた社内版チェックリストや掲示用A4ポスターのデータも作成します。お気軽にご相談ください。